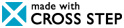茶道を通して美しい所作を学び、自然を大切にする心を育む「名月会」
2011.04.07
「美しきもの」を愛でるには、本物に触れてこそ。

周囲に古寺が点在する、鎌倉の浄明寺にある宗偏流家元邸。門をくぐると、せわしない日常とは一線を画す穏やかに流れる澄んだ空気。茶道会館までの長いアプローチを歩く間に心がすーっと落ち着き、と同時に背筋が伸び、これから始まるお稽古への心の準備が自然に整います。
 「名月会」は宗偏流の家元夫人、山田宗里さんが10年ほど前に始めた、幼児から小学生を対象としたした茶道教室。昔から「芸事は6歳の6月6日から」習うものとされているそうですが、宗里さんのお嬢さんが2歳になった頃に茶道具に興味を持ち始めたのを見て、これならば早い時期にスタートさせてもいいのでは、ということで始めたのがきっかけでした。
「名月会」は宗偏流の家元夫人、山田宗里さんが10年ほど前に始めた、幼児から小学生を対象としたした茶道教室。昔から「芸事は6歳の6月6日から」習うものとされているそうですが、宗里さんのお嬢さんが2歳になった頃に茶道具に興味を持ち始めたのを見て、これならば早い時期にスタートさせてもいいのでは、ということで始めたのがきっかけでした。「子どもたちには洞察力を養って欲しい」との願いから、茶道具に使用される鉄、漆といったさまざまな本物の素材を手にしたり、和ろうそくのほのかな灯りや、お湯を沸かす釜のしゅんしゅんという音など、直接の体験を活かして五感を研ぎ澄ませる機会をたくさん設けています。
レベルに応じて3つのクラスに分けられ、それぞれにひとりずつ先生がついてお稽古をしていきますが、まずは皆が揃って礼儀の基本である挨拶から。そして近況を報告し合い、お茶をいただくときの心得である喫茶呪文を唱え、床の間にある掛け軸を見て、それぞれにどんなことを感じたかを発表します。ちなみに今回は柳の絵が題材でした。

掛け軸を前にして正座。どんな風に感じるか、自分の心に問いかけてみる。

炭点前(すみてまえ)のクラスでは炭を箸で掴み、一つひとつの並べ方や種類などを学んでいく。
お茶席で目の当たりにした子どもたちの成長ぶり。

力囲席のクラスの様子。先生が正面に座り、一挙手一投足をじっと見つめている。
今回取材をした椅子に腰かけてお茶を点てる力囲席(りきいせき)のクラスでは、一度茶道会館を出て路地を通り、庭を抜けて力囲席と呼ばれる茶室へ移動します。室内には家元が特別に発注した、力囲棚(りきいだな)という茶道用バーカウンターが。伝統とモダンを融合したデザインと、窓の外に広がる木々や滑川の上流といった自然の風景が相まった空間美には、思わずため息が漏れるほど。この贅沢な空間で、道具の扱い方から点前までひと通りを教わっていきます。
 今回取材をした椅子に腰かけてお茶を点てる力囲席(りきいせき)のクラスでは、一度茶道会館を出て路地を通り、庭を抜けて力囲席と呼ばれる茶室へ移動します。室内には家元が特別に発注した、力囲棚(りきいだな)という茶道用バーカウンターが。伝統とモダンを融合したデザインと、窓の外に広がる木々や滑川の上流といった自然の風景が相まった空間美には、思わずため息が漏れるほど。この贅沢な空間で、道具の扱い方から点前までひと通りを教わっていきます。
今回取材をした椅子に腰かけてお茶を点てる力囲席(りきいせき)のクラスでは、一度茶道会館を出て路地を通り、庭を抜けて力囲席と呼ばれる茶室へ移動します。室内には家元が特別に発注した、力囲棚(りきいだな)という茶道用バーカウンターが。伝統とモダンを融合したデザインと、窓の外に広がる木々や滑川の上流といった自然の風景が相まった空間美には、思わずため息が漏れるほど。この贅沢な空間で、道具の扱い方から点前までひと通りを教わっていきます。 日頃のお稽古の成果は、各クラスの子どもたちだけの初釜(新年に行われるお茶会)や雛の茶会といった発表会で披露してきましたが、先日、政治家の河野太郎氏を席主に招いて外部のお茶会で薄茶席を持ったときのこと。まさか子供ばかりがお茶席に登場するとは思ってもみなかったゲストの方々は驚き、いろいろな質問を投げかけたそうです。しかし心乱すことなく「どの子も落ち着いて淡々と答えながら、手を止めずに次々と点前を進めていきました」その姿を見て、宗里さんは子どもたちの中に芽生えた動じない心、そして時折垣間見えるリーダーシップやチームワークの力をきちんと身につけている、と実感したと言います。
日頃のお稽古の成果は、各クラスの子どもたちだけの初釜(新年に行われるお茶会)や雛の茶会といった発表会で披露してきましたが、先日、政治家の河野太郎氏を席主に招いて外部のお茶会で薄茶席を持ったときのこと。まさか子供ばかりがお茶席に登場するとは思ってもみなかったゲストの方々は驚き、いろいろな質問を投げかけたそうです。しかし心乱すことなく「どの子も落ち着いて淡々と答えながら、手を止めずに次々と点前を進めていきました」その姿を見て、宗里さんは子どもたちの中に芽生えた動じない心、そして時折垣間見えるリーダーシップやチームワークの力をきちんと身につけている、と実感したと言います。「当時は幼児を対象に考えていましたが、嬉しいことに生徒たちがついてきてくれて、現在に至ります。今の考えとしては子どもたちの人生のステージが変わっていく中、ここだけはずっと同じというような、いつでも帰ってこられる拠り所であったらいいな、と思っています」
小さいうちから本物に触れて感性を磨き、自然の中に身を置いて季節を感じ、所作を学んで場の空気を心地良いものにする──。
茶道イコール、たくさんの決まりごとがあって堅苦しいものと思われがち。けれども、正しい立ち居振る舞いや言葉遣いを通して物事の本質を掴んだり、美しいもの、価値あるものを素直な心で受け止めて感動したりするための絶好の習いごとなのだと、子どもたちの取り組み方を見て、そう感じました。
茶道イコール、たくさんの決まりごとがあって堅苦しいものと思われがち。けれども、正しい立ち居振る舞いや言葉遣いを通して物事の本質を掴んだり、美しいもの、価値あるものを素直な心で受け止めて感動したりするための絶好の習いごとなのだと、子どもたちの取り組み方を見て、そう感じました。

最後に皆で揃って、礼。